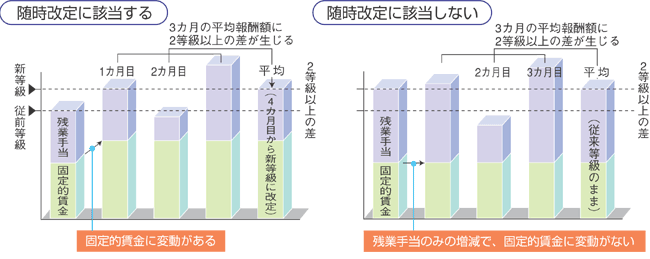|
月額変更届(随時改定)の実務
|
|||
|
■随時改定が必要となるとき 被保険者の報酬月額が大幅に変動して、次の①~③のすべての条件に当てはまるときは随時改定に該当するため、事業主は年金事務所に「報酬月額変更届」の提出が必要になります(健康保険組合や厚生年金基金に加入している場合は、それぞれ届を提出)。 (1)固定的賃金が変動、または給与体系の変更があった 固定的賃金の変動とは、継続して支給される一定額の賃金や手当てに、昇(降)給や支給額変更、日(時)給の基礎単価や請負給・歩合給などの単価・歩合率の変更などがあった場合をいいます。 (2)変動月以後引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日以上ある 昇(降)給などにより支給の変動があった月を変動月といいます。遡り昇給などで差額を支給したときは、実際に差額を支給した月が変動月になります。 (3)変動月以後、引き続く3ヵ月間の報酬総額の平均額が、現在の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じた 変動月から継続した3ヵ月間の報酬の平均による標準報酬月額等級とすでに決定されている標準報酬月額等級との差が2等級以上ある場合は随時改定に該当します。固定的賃金に多少でも変動があれば、残業手当など非固定的賃金を加えて結果的に2等級以上の変動になる場合でも該当します。 ■パートタイマーの随時改定 短時間就労者の随時改定時における標準報酬月額の算定の場合も、継続した3ヵ月のいずれの月も支払基礎日数が17日以上であることが必要となり、定時決定で算定対象としている15日以上17日未満の月は随時改定の場合は対象となりません。 ■随時改定に該当しないケース 固定的賃金に変動がない場合は、非固定的賃金の変動だけで2等級以上の差が生じたとしても、随時改定に該当しません。 ■上・下限の取扱い 健康保険・厚生年金保険ともに標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりません。しかし、それぞれに標準報酬月額の上下限が設けられているため、最高(低)等級の1等級下(上)に該当する人は、どんなに報酬月額に増額(減額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。このような場合、例外として1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じたとみなして、随時改定を行います。 ■保険者が行う修正平均 変動月以降の継続した3ヵ月のいずれかの月に昇給差額の遡り支給などがあった場合、3ヵ月の報酬の平均額で標準報酬月額を改定すると、実際の報酬額とかけ離れてしまうことになります。
<図をクリックすると拡大されます> |
|||